
新しい企画を考えたいのに、メール、議事録、資料作成に追われ、なかなか「考える業務」に手を付けれない―そんな経験ありませんか?
生成AIを仕事に取り入れると、日々のルーティーンワークを効率化し、より重要な仕事や考える業務に時間を使えます。
今回は、数ある生成AIツールの中でも、人気のChatGPTを使って、実際に私が月に約20時間もの業務時間の削減に成功した事例を、職種別の使い方・注意点とあわせてご紹介します。
ChatGPT(生成AI)の導入で何が変わる?期待できる3つの効果

ChatGPTを仕事で使うと、作業効率だけではなく、仕事の判断の質も変わります。
本章では、ChatGPTを導入することによって期待できる3つの効果を解説します。
単純作業が短時間で終わるようになる
ChatGPTの導入により、時間のかかる単純作業を効率的に処理できるようになります。
実際に私は、定型メールや資料のたたき台をChatGPTに出してもらい、今まで1時間かかっていた作業が約10〜15分まで圧縮できました。
ルーティン業務が減れば、本当にやるべき仕事に時間を使えます。
その結果、同じ人数でも仕事が終わる時間が早くなるのです。
文章作成の効率が上がり、発信が楽になる
「頭ではわかってるのに、文章にしようとすると手が止まる…」、こんなことありませんか?
文章の作成や表現の工夫が必要な場面でも、ChatGPTは非常に心強い存在です。
例えば、社内報や顧客へのメール、SNS投稿などのたたき台もChatGPTに作ってもらうことができます。
ポイントをChatGPTに箇条書きで伝えるだけで、ほんの数十秒でたたき台ができあがります。
下書きがあれば、あとは加筆・修正だけで済み、取りかかりの負担がぐっと軽くなります。
言い回しの候補が複数出るので、トーン合わせも短時間で行うことが可能です。
「考える」仕事の質が上がる=本来の仕事に集中できる
日々のルーティーン業務をChatGPTに任せることで、顧客対応やクリエイティブな仕事など、人にしかできない部分に時間を回せます。
余裕ができるとミスが減り、いいアイデアも出やすくなります。
つまり、同じ頑張りでも、結果が全然違ってくることが大きなメリットです。
ChatGPT(生成AI)を使って業務効率化しよう|時短アイデア8選

ChatGPTって、「文書作成のAIでしょ?」—いいえ、それだけではないんです。
ChatGPTは、文書作成はもちろん、情報整理、アイデア出しなど、様々な仕事で役立ちます。
本章では、私も実際に使っている便利な使い方から、効果を実感しやすいアイデアまでを、8個に厳選して紹介します。
定型メールの作成と返信文のドラフト
1日の業務の中で、メール対応に想像以上に時間を費やしていませんか?
1通にかかる時間は数分でも、件数が重なるとあっという間に1〜2時間消えることもありますよね。
メール対応に時間を費やしている人は、一度ChatGPTを使ってみてください。
挨拶文や依頼文、報告メールなどの定型文を瞬時に作成してくれます。
例えば、「納期延長のお願いのメール文章を、先方に失礼のないように、200〜300字で書いて」のように、条件を具体的に伝えると効果的です。
下書きを作成してもらったあとは、肉付けや手直しをして、そのまま使用することができるので、とても便利です。
会議議事録の自動要約と要点整理
会議の議事録作成、ついつい後回しにしがちではないでしょうか?
私はつい後回しにしてしまうタイプです。
ChatGPTにメモを読み込ませれば、決定事項・担当者・期限などの要点を短時間で整理できます。(※ChatGPTでは録音した音声データをテキストに変換できないので、別ツールを併用する必要があります)
話し合いの中で出た重要なトピックや、決定事項を箇条書きにすることも可能です。
ChatGPTを使うことで議事録の共有スピードが上がり、要点整理をすることで抜け漏れの防止にもつながります。
資料のたたき台やキャッチコピー案
資料作成の際、最初の書き出しで手が止まること、ありませんか?
ChatGPTは、事前のリサーチや、企画書、提案書の構成案、リード文、見出しなど、資料作成のベースを作る際にも活用できます。
また、タイトルやキャッチコピーの候補も同時に作ると、ゼロから悩む時間が消え、方向性も自然と決まってきます。
時間短縮とアイデア出しの両方ができる点が魅力です。
商品説明文・セールスコピーの提案
ECサイトや営業資料などで使用する商品説明文やセールストークも、ChatGPTがサポートしてくれます。
例えば、ターゲット・使用シーン・差別化を入力し、トーン違いで3案生成してもらい、それをECや営業資料のABテストにそのまま使うことも可能です。
検証で手応えのある表現を残せば、その後の制作が楽になります。
企画のアイデア出しと壁打ち対話
「新しい企画を考えたいけれど、アイデアが出てこない」と感じたときにも、ChatGPTは役立つ存在です。
質問をしたり、ざっくりした構想を伝えたりするだけで、壁打ち相手のように対話形式でアイデアを掘り下げてくれます。
独りよがりになりやすいブレストも、ChatGPTに投げることで客観性が増し、アイデアが広がります。
社内マニュアル・FAQ作成の下書き
社内向けの手順書やFAQを作る際、白紙から書くのは予想以上に大変ですよね。
ChatGPTに業務内容を入力するだけで、「よくある質問」とその回答例や、手順を箇条書きにまとめた草案を作ってくれます。
作成の負担が減り、整った資料をすぐに用意することができます。
SNS投稿文の生成・言い回しのリライト
SNS運用において、魅力的な文章の案出しは、手作業だとどうしても時間がかかりますよね。
ChatGPTは、文章の案を出すだけではなく、複数の言い回しを提案したり、ペルソナに合わせてトーンを調整することも可能です。
表現のバリエーションが増えるほど、SNSの成果向上にもつながります。
作業タスクの要点整理と優先順位づけ
タスクが多くて、「何から手をつけようか」と迷うこと、ありませんか?
ChatGPTにやるべきことを入力すると、目的や緊急度に応じて分類や整理をしてくれます。
【例】目的/緊急度/誰かに頼る必要があるか、の3つで並べ替え、今日やること・やらないことを決める。
私も実際に使いますが、頭の中を整理しながら業務の優先順位を決めたいときに、非常に便利です。
【業種・職種別】ChatGPT(生成AI)活用事例まとめ

ChatGPT(生成AI)の使い方は、業種・職種によって、効果的な使い方が異なります。
本章では、職種ごとのリアルな活用パターンを紹介し、どのように日々の仕事に役立てられるのかを具体的に説明します。
営業職|提案書やアプローチ文の作成補助
営業職では、クライアントに合わせた資料やメールの文面を素早く整える力が大切です。
ChatGPTを使えば、提案書の構成案や、初回連絡メールの文面を短時間で作成することができます。
導入ストーリー(現状課題→解決策→導入手順→期待できる効果)、費用対効果、想定Q&Aを一式準備し、業種・役職に合わせて語り口を調整します。
初回連絡メールの文面も同時に用意でき、準備は短く、説得力は高くすることが可能です。
事務職|定型文処理・マニュアル化の効率化
日報、報告書、各種申請メールなど、事務職では定型文業務が多く発生します。
ChatGPTを使えば、過去のメール文や業務手順を元に、フォーマットの文面を瞬時に生成することが可能です。
さらに、社内用の手順マニュアルやFAQの草案も短時間で用意できるため、属人化の防止にもつながります。
マーケター|キャッチコピー・LP構成の発案
マーケティング業務では、訴求軸×ペルソナ×使用シーンでパターン展開をすると、方向性の比較がしやすいです。
ChatGPTを使えば、キャッチコピーの候補を複数提案してくれたり、LP(ランディングページ)の構成案を考えてくれたりします。
例えば、「20代女性向けコスメの魅力を伝えるコピーを3つ考えて」などの指示も有効です。
アイデア出しで困ったときに、非常に心強い存在です。
エンジニア|コード生成・仕様整理のサポート
エンジニアにとっても、ChatGPTは「説明のいらない補助ツール」として使えます。
簡単なHTMLやPythonなどのコードを生成したり、処理フローを整理したりと、技術的なタスクの効率化が可能です。
「エラーの原因を教えて」「この仕様でどう実装すればいい?」といった相談にも対応してくれます。
特に勉強を始めたばかりの人や、非エンジニアとのブリッジ役としても優秀です。
経営者・個人事業主|日報作成・施策検討の効率化
経営者や個人事業主は、タスクが多岐にわたるため、情報整理が重要です。
ChatGPTを使えば、日報や業務報告の文章化、アイデアの整理、実行施策の比較検討などが効率化されます。
「今月の反省点をもとに、来月の施策を考えて」といった問いかけで、思考の整理や方向性のヒントも得られます。
一人経営や少人数組織でも、作業と思考を同時に支援してくれる存在です。
「ChatGPT(生成AI)は難しそう」と感じる人のための導入ステップ

ChatGPT(生成AI)に興味はあっても、「使いこなすのが難しそう」と感じていませんか?
しかし、実際の導入はシンプルな一歩からで十分です。
本章では、初心者でも迷わず始められるように、導入時の考え方や設定のコツ、社内展開のポイントを紹介します。
「何に使うか」を決めてから始めるだけで変わる
ChatGPTを業務で使用する際は、「まず使ってみる」よりも「何に使うか」を明確にすることが成功の鍵です。
「毎朝のメールだけ」「議事録だけ」など用途を一つに絞ります。
目的が明確だと、出力結果の評価もしやすく、継続的な使用につながります。
最初は1業務・1プロンプトで十分です。
まずは3つの基本プロンプトを覚えよう(例付き)
ChatGPTを使いこなすには、まず「良い問いかけ=プロンプト」を考えることが大切です。
以下の3つは汎用性が高く、初心者でもすぐ使える例です。
- 【例1】「この文章を、ビジネス向けに整えて。語尾はです・ます調で統一」
- 【例2】「○○業界のトレンドについて、箇条書きでまとめて」
- 【例3】「SNS投稿文を、カジュアル・やさしい言い回しで140字で3案出して」
このような指示を繰り返すことで、自然と「伝え方」が身についていきます。
テンプレートのように使えるプロンプトを3つ用意しておくだけで、運用が格段に楽になります。
失敗しない始め方|無料版・GPTsの使い分けと設定方法
ChatGPTには無料版と有料版(ChatGPT Plus)があります。
最初は無料版でも十分に効果を実感できます。
有料版ではGPTs(カスタムGPT)を使った、高度な運用も可能です。
初心者がつまずきやすい初期設定や使い分けのポイントは以下のとおりです。
| 項目 | 無料版(GPT-5) | 有料版(GPT-5) |
| 使用コスト | 無料 | 月20ドル (約3,000円) |
| 精度 | 高精度。上限後は GPT-5 mini に切替でやや精度低下 | 常時高精度・長文対応 |
| GPTs使用 | 利用可能 (閲覧・利用) | 利用可能 (作成・利用) |
まずは無料版で業務支援を体験し、「もっとできることがありそう」と感じたタイミングでアップグレードすると無駄がありません。
社内で共有するなら「成果物を見せる」ことが鍵
社内にChatGPTの活用を広める場合は、「これは便利そう」と思わせる成果物の共有が効果的です。
たとえば、以下のような事例がよく使われます。
- 議事録が要点だけに整理されていて見やすい
- SNS投稿文がすぐに使える状態で出力されている
- 複数案のコピーが1分で出てくる
便利さを体験で共有すると、社内の賛同が得やすくなります。
ツールの説明よりも“出力例”を見せることが導入の近道です。
ChatGPT(生成AI)を使用するうえで気をつけるべき5つの注意点
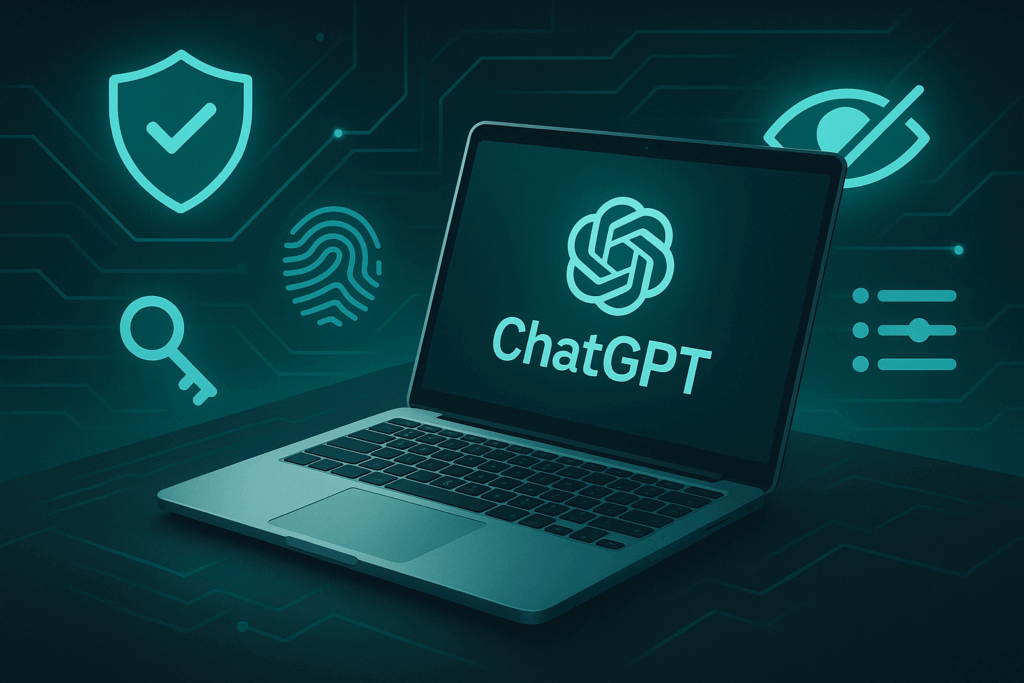
ChatGPT(生成AI)は非常に便利です。しかし、使い方を誤るとリスクやトラブルの原因にもなりかねません。
本章では、業務でChatGPT(生成AI)を安全かつ効果的に使うために、最低限押さえておくべき注意点を5つ紹介します。
機密情報・個人情報は入力しないことが大原則
ChatGPTに入力した内容は、原則として外部に共有されることはありませんが、「絶対に安全」とは言い切れないので注意が必要です。
会社名や氏名、金額、メールは絶対に入力しないこと。
業務に使う場合は、「個人を特定できない抽象化された内容にする」などの工夫が必要です。
生成された内容は必ず事実確認をする
ChatGPTの回答は正確のように見えて、間違った情報や古い情報を含む可能性もあります。
例えば法律、医療、統計データなどの専門分野では、必ず信頼できる一次情報で照合することが必要です。
出力内容を鵜呑みにせず、人の目でチェックすることが、安全な運用につながります。
回答のトーンや語尾を目的に応じて調整する
ChatGPTは、指示をしなければデフォルトの「やや丁寧」な文章で出力されます。
しかし、社内メール・広報資料・営業文書など、用途に応じて「フレンドリーに」「もっと丁寧に」「カジュアルに」などトーンや語尾を調整する指示が必要です。
目的に合わせた出力ができるよう、プロンプト内にトーン指定を含める習慣をつけましょう。
「全自動」ではなく「共創ツール」として使う
ChatGPTは万能ツールではなく、人間と協力して作業を進める「共創パートナー」のような存在です。
完全に任せてしまうのではなく、ベース案を作らせて、そこから人の目で修正することが理想的な使い方です。
この意識を持つことで、出力内容の品質や使い方の幅も広がります。
社内に広める際のルール作りや研修の必要性
業務ツールとして社内で展開する場合は、使い方のルール作りと研修は必須です。
例えば「個人情報の扱い方」「出力の事実確認の義務」「テンプレ化されたプロンプト集の共有」などが該当します。
特に情報リテラシーにばらつきがある組織では、導入初期のガイドラインづくりがトラブル回避につながります。
まとめ|まずは「今すぐ楽にしたい業務」から始めよう

ChatGPT(生成AI)を活用すれば、月約20時間の削減も夢ではありません。
そのために必要なのは、すべてを自動化しようとするのではなく、「1つの業務を楽にする」ことから始めることです。
例えば、「メールの文面を早く作れるようにしたい」「SNS投稿の言い回しを整えたい」など、すぐに効果が実感できる作業から取り入れてみましょう。
効率化に加えて、企画や戦略を練る時間が増えたり、アイデアの質が上がるなど、業務の“質”そのものが変わっていくことも感じられるはずです。
今日、1タスクだけAIに振ってみてください。
小さな一歩が、大きな時短と業務改善につながります。まずは気になる業務1つから、ぜひ始めてみてください。
(※効果は職種や運用によって変わります。本記事は筆者の利用経験と公開情報に基づく参考情報です。)